ねこみです。
長男ぽにおはASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けています。小学校入学した時から、放課後の居場所として放課後等デイサービスを利用してきました(小学校入学に関しての記事はこちら)。
ひとことで放課後等デイサービスと言っても、実はいろいろなタイプがあるんです。
この記事は種類ごとの特徴と、利用の流れ、そして我が家の体験談を紹介します。
放課後等デイサービスって?
預かり型
ぽにおが最初に利用したのは「預かり型」と呼ばれるタイプ。
少人数で過ごしつつ、遊んだり日替わりのプログラムをしたり宿題をしたり…と比較的のびのびした印象でした。
特に助かったのが長期休み。
夏休みも冬休みも朝から迎えに来てくれて、夕方18時ごろに送り届けてくれるので、ワーキングマザーにはなくてはならないサービスでした。
また、小学校1年生からずっと一人の支援員さんにお世話になっていて、その方が独立された時にはその方について新しい事業所に移動をしました。
そのため、長いお付き合いのその方は、ぽにおにとって第二の母のような存在。それがとてもありがたいなと思っています。
運動特化型
次に利用したのはスポーツに特化した放デイ。
ぽにおが通っていたところは、サッカーやボルダリングやトランポリン等…多彩なプログラムがありましたが、その中でぽにおは水泳のプログラムの日に利用していました。これが、とてもいい選択だったのです。
体力がついて喘息の発作も出なくなり、泳ぎもどんどん上達して、最終的にはバタフライまで泳げるようになりました。
ただ、預かり型とは違い、朝早くに迎えに来てもらうことは難しく、長期休みの時には自分の仕事の都合をつける必要がありました。
学習特化型
学習塾のような放デイも、最近は増えています。
高校生となったぽにおは、近所の放デイで行っている有償ボランティアの学習支援を受けていますが、勉強が習慣づいてきている実感があります。
親が勉強を見ると、どうしても歯がゆくなっちゃって、「なんでわからないの!キィー!!」となってしまいがち。外で勉強してきてくれることで、どれだけ助けられたことか。
ただし、このタイプは送迎がない場合が多いので要確認です。
また、一部には通信制高校と提携している放デイもあります。通って課題を提出したり、たまにスクーリングをして高校卒業資格がとれるという、なんともありがたいシステム。
実はぽにおの高校進学を考えるタイミングで、この選択肢は候補にありました。専修学校に通っている今も、何かあった時の受け皿に…と、心の中のお守りにしています。
【参考】最近増えている放課後等デイサービスのタイプ
我が家では利用経験はありませんが、見学や情報収集の中で、次のような放デイも見かけました。
- 個別療育
- マンツーマンや少人数での支援が中心。集団が苦手な子や、静かな環境が合う子向け。
- 武道療育
- 空手などの武道の動きや礼節を基にした運動療法。
- プロミング、ICT系
- 発達支援の一環として、論理的思考や問題解決力等を培うことができる。
見学だけじゃない!利用前にちょっと気を付けてほしいこと
それは、「口コミ」です。
これは上記にも書いた、ぽにおが9年間も水泳でお世話になった運動特化型のデイのこと。
利用当初にママ友から
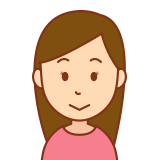
正直、あそこはいつか何か起きそうで怖い。
と言われたことがありました。
当時はほかに選択肢も少なく、定期的に水泳の指導を受けられる貴重な存在だったため、そのまま利用を続けていました。
しかしある日、
本来確認されるはずだった「自宅への入室と施錠」を、未確認のまま送迎職員が帰ってしまい、ぽにおが1時間以上、自宅前で締め出されるという事故が起きました。
ぽにお曰く、日頃より確認はされていなかったそうです。そして、たまたま鍵を忘れてしまったその日、事態が明るみに出たのでした。
市への事故報告と謝罪はありましたが、直接関わった職員の対応には「自分事として受け止めていない」印象を強く受けました。
この経験から感じたのは、見学やパンフレットだけではわからない「人の姿勢」や「現場の空気」があるという事。
そしてそれを教えてくれるのは、実際に長く利用している保護者の声なのだと思います。
まとめ
放デイは多様化しており、それぞれに特色があります。
また、特性を持った繊細な子供たちが通うところですから、親が「良い」と思ったとしても、それが絶対ではありません。
デイを利用していて、我が家に実際起こったことで言えば、
- 支援員さんとの相性
- 同じ学校から通っている子がいるか(その子のことが得意か苦手か)
このような理由で、利用の曜日を減らしたり変更したり…ということがありました。
まずはいくつか見学をして、お子さんに合うかどうかじっくり検討するのがいいと思います。
そして、「有名だから」「プログラムが魅力的だから」だけで決めず、実際に利用している保護者の声にも、ぜひ耳を傾けてほしいと思います。
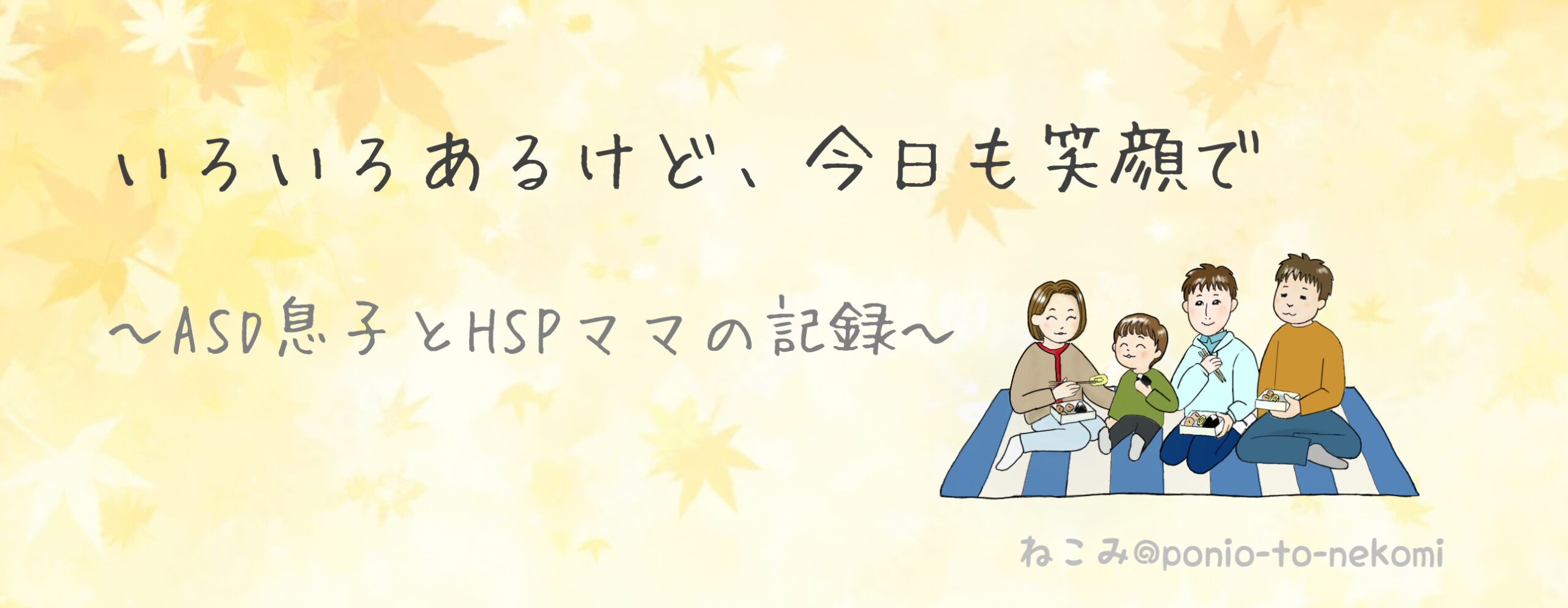
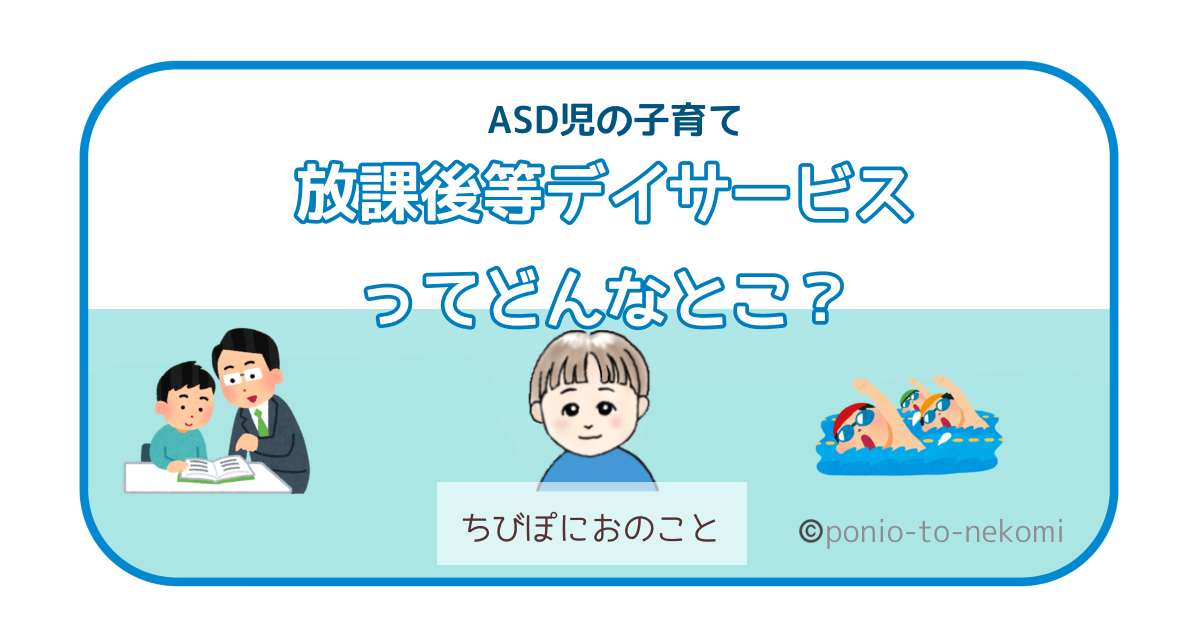


コメント