ねこみです。
我が家の長男ぽにおはASD(自閉スペクトラム症)です。
小中は支援学級に通ってきましたが、卒業後は専修学校に進学し、今は高校生です。
この記事では、なぜ専修学校を選んだかを書いていきます。進路に悩む誰かの参考になりますように。
シリーズ①はこちら。
親の葛藤
「支援学級からの進路」については、前回の記事(シリーズ①)で書いた通り、ほとんどの子が特別支援学校に進学します。
しかし、ぽにおは小学校4年生から療育手帳非該当でした。
かと言って余裕の非該当ではなくて、ギリギリ非該当。ワーキングメモリや処理速度は下手したら年齢の半分くらいなのに、言語能力が年齢相応なので、全体的に高く出る傾向がありました。(これはやっぱり、小さなころから買い与えてきた図鑑や、大好きなマインクラフトの力だと思います。質問になんでも答えられちゃう。)
つまり、頭ではよくわかっているんです。これを実行することがとても遅い。そしてすぐ忘れる。
親としては、「支援」の枠で守ってあげたい気持ちと、本人の理解力や頑張りを信じてあげたい気持ちで揺れていました。
「手帳」という選択肢
発達検査を受けるたび数値が上がるぽにお。
でもそれは、IQが上がっただけの話であって、「社会性」や「こだわり」「幼さ」が劇的に改善されたわけではありません。
ましてや、ギリギリの非該当。
もしかしたら、少しだけ手を抜いて挑めば(正直に言えば、ちょっとだけわざと間違えたら)手帳がとれるかもしれないと考えることもありました。
なぜなら、手帳があることで経済的な負担が軽くなり、将来は障害者枠での就職など、より安定した進路につながる可能性があるからです。
でも私たちは、ぽにおが小さいころから大切にしてきた「正直に自分の力で頑張ること」を裏切ることはできませんでした。
どんなことでも、まじめに取り組んだことを褒め、結果がよければさらに褒めてきました。発達検査の時だって、もちろん同じ。
ここで「手帳を取るために力を抜く」という選択をしてしまえば、それまで積み重ねてきた私たちの方針を自ら否定するようなものだと思いました。
こうして私たちは「手帳非該当」を受け入れ、支援学校を選択肢から外しました。
専修学校という選択
専修学校は候補が3校あり、どの学校も複数回足を運びました。
A校…厳しい校風でまじめな生徒が多い。商業系。片道1時間20分。
B校…寛容で自由な雰囲気。発達障害児への手厚さで言えば一番。商業系。片道40分。
C校…体育会系の校風。B校よりも発達障害児への理解は少なめ。工業系。片道1時間10分。
本人の感触や通いやすさからB校とC校に絞り、最後は授業の様子も見せていただきました。
B校の手厚さと通いやすさは魅力でしたが、ぽにおは電気科のあるC校に強く惹かれていました。
どうせ学ぶなら、本人が興味を持てる内容の方がいい。そう考え、最終的にC校を特別専願で受験することに。
入試は筆記と面接がありましたが、無事に合格をいただくことができました。
入学してみての現実
さて、合格はしたものの、私はとっても不安でした。なぜならぽにおは一人で公共交通機関を乗り継いだことがなかったからです。
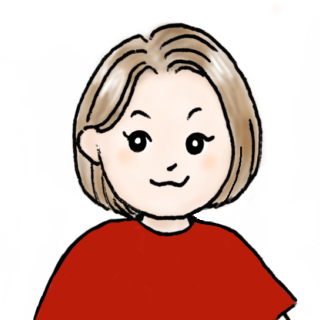
ちゃんと通えるかな。
乗り換えを間違えたりして、途中でパニックにならないかしら…。
でも、そんな私の心配をよそに、今のところ毎日通えています。体調不良以外では休まず、無遅刻。本人なりに、とってもがんばっています。
もちろん、成績は下から数えたほうが早いです(笑) 。一学期からさっそく一教科で赤点を取り、追試も経験しました。
それでも、朝自分で起きて、準備して、電車に乗って学校へ行く。それだけで十分と、今は思っています。
これが現実です。「支援学級から高校へ行く」ってこと。
まとめ
支援学級からの進路は、支援学校以外にもいろいろとありますが、どの道にも良いところと大変なところがあります。
我が家の場合は、本人の気持ちや能力などを考えて「高校生になる」道を選びました。そして、先に触れたとおり、すでにいくつもの壁にぶち当たったりもしています。
でも、そのたびに少しずつ成長を実感し、不安もあるけど挑戦する姿を見守りたいと思っています。
さて、次回【高校進学シリーズ③】はお金の話です。入学にはいくらかかったのか。授業料無償化って、実際いくら戻ってくるのか。実際に通ってみてわかった「経済的なリアル」についてまとめます。
余談ですが…
ぽにおが小1の時の担任の先生との、忘れられないやりとりがあります。
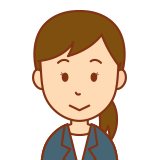
支援学級の子は高校生にはなれません。みんな支援学校に行くんですよ。
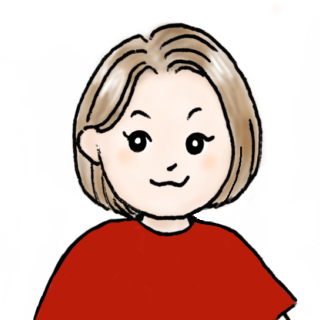
え?内申点がなくても行ける高校はありますよね?
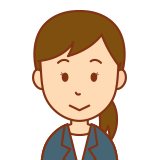
そんな高校あります?
だって!
その先生に今会ったら言ってやりたい。
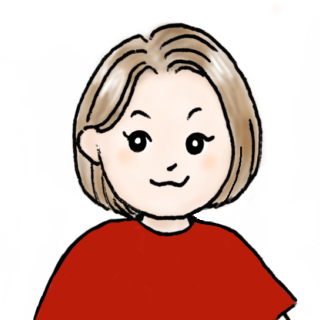
内申点なくても行ける高校、ありましたよ。
先生なのに、そんなことも知らないんですかー?
って(笑)。
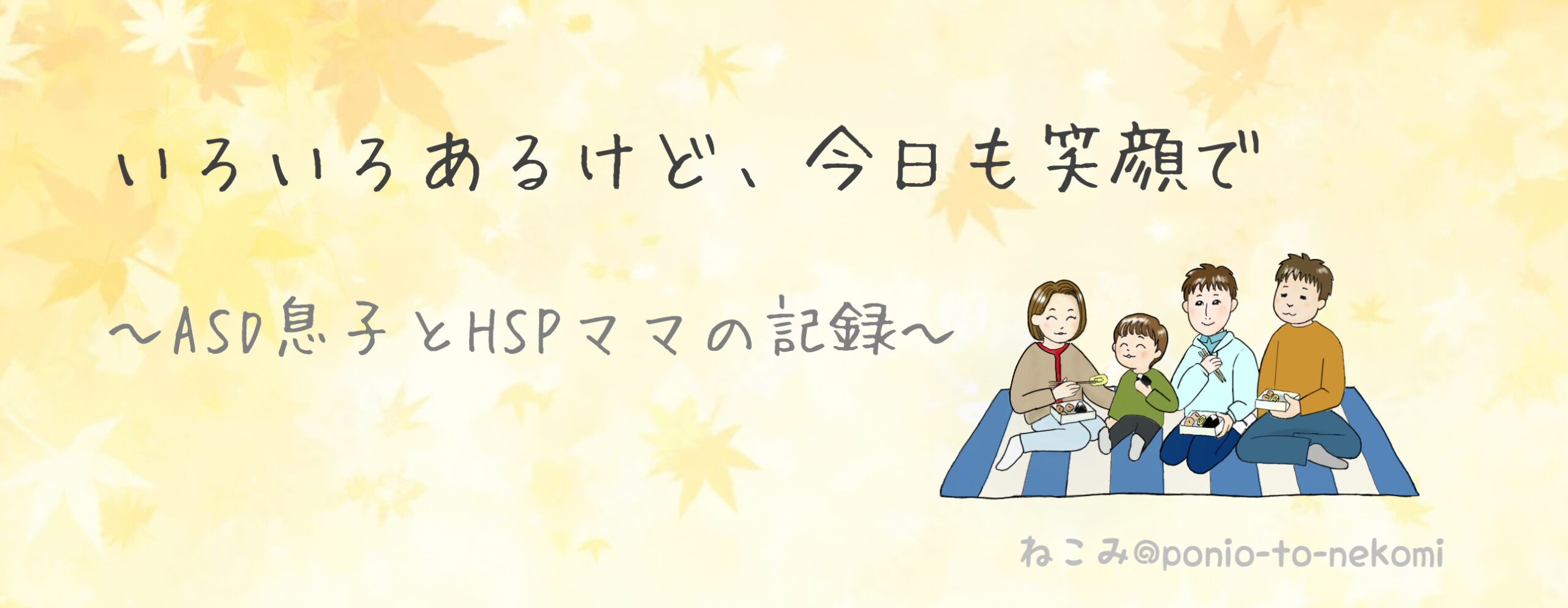
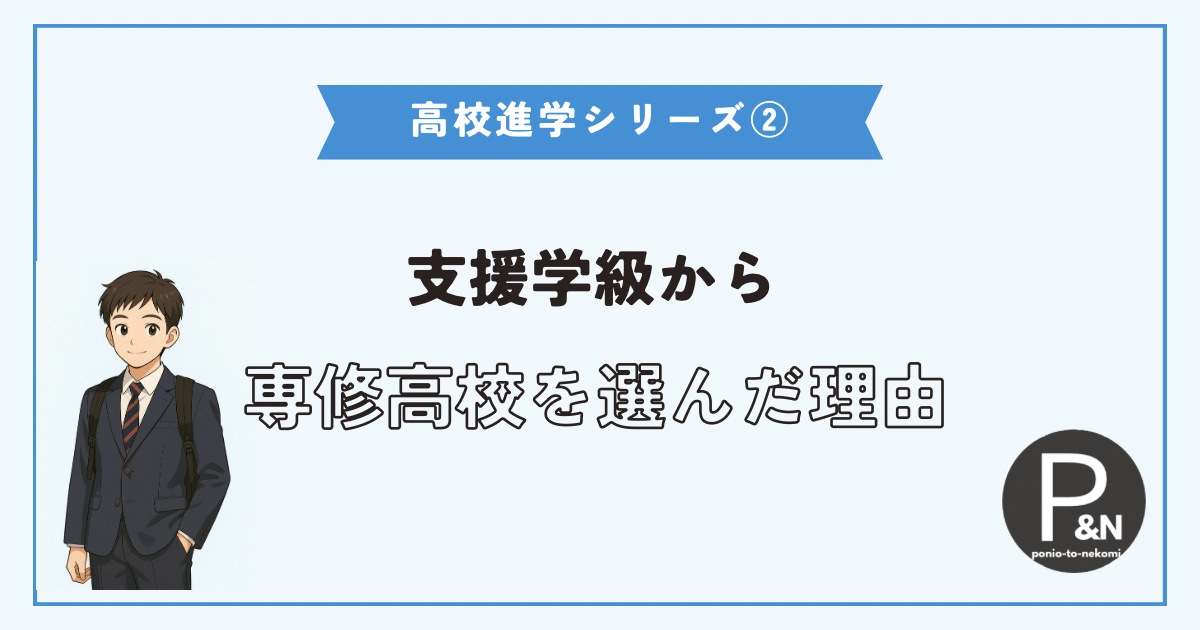


コメント