ねこみです。
長男ぽにおはASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けています。
言葉が遅かったので、私はぽにおの保育園の同級生がいっぱいおしゃべりするのを見ては、「うちの子もいつかあんなにしゃべることができるかしら」とうらやましく思っていました(前回の話はこちら)。
5歳、それは突然やってきた
ある朝、私はぽにおにゆすり起こされます。
「ねえお母さん、ジャイアントインパクトって知ってる?昔ね、原始地球に火星ぐらいの大きさの惑星がぶつかってね…」
え、なに?😮いったい何が起こっているんだ。
それまで2語文やオウム返しがメインだったぽにおが、突然文章でしゃべるようになりました。この時5歳、惑星の図鑑を購入してしばらく経ったころのことでした。
それもまた、朝から晩までしゃべるしゃべる…。
それまで、ぽにおがしゃべる時は手を止めて、目の高さを合わせてじっくり聞いていた私。でも、すごいしゃべるようになったものだから、それをやってたら何にもできない!
というくらい。うれしい悲鳴でした。
小さな希望を信じて積み重ねてきた時間が、ようやく実を結んだ瞬間でした。
止まらないおしゃべり
待ちに待った文章でのおしゃべり。
時間の許す限り、ぽにおのおしゃべりを「うん、うん」と聞いたものでした。せわしなく動くお口がいとおしくてたまりませんでした。
でも、同時に困ったことも出てきます。
ぽにおは自分がしゃべりたいことを聞いてはほしいけど、こちらが聞きたいことにはあまり答えてくれませんでした。
好きなことは饒舌に語り、相手の話には興味なく、ついでに言うと、飲食店だろうが公共交通機関だろうがおかまいなし。せっかくおしゃべりができるようになったのに、これではコミュニケーションを楽しめない(主に相手が)!
これは、この先の小学校生活でも「課題」であり続けました。
家庭でできる療育「糸電話」
さて、そのころ私はぽにおと「会話」をしたいときに糸電話を使っていました。
- 話を聞く訓練になる
- 引っ張りすぎず緩すぎず、力加減を教えられる
- 自分の声の大きさを知ることができる
糸電話は自閉症児におすすめの遊びです。
これは、たまたま私一人で出かけているときに、出先から自宅にいる主人に電話をして、電話口を変わったぽにおが意外にもしっかり受け答えができたという、ちょっとした発見がきっかけで始めたことでした。
電話って、基本的に一問一答だから、ぽにおも答えやすかったのだと思います。
スモールステップという考え方
何かできるようになれば、新しい「課題」が出てくる。
その、乗り越えるべき「課題(ハードル)」を通常より低めに設定してあげると、発達障害とうまく付き合っていくことができます。
例えば、「晩御飯何食べたい?」と聞けば、5歳程度の子供たちは「ハンバーグ」「お寿司」「オムライス」などと答えるところ。
5歳のぽにおに対してはこのように聞いていました。「今日の晩御飯、カレーがいい?パスタがいい?」
二つの選択肢から選ぶだけなので、だいぶハードルが低くなります。答えやすい質問を心がけて関わりました。そして、だんだんと多くの選択肢から選べるようになり、そのうち「いや、今日はうどんの気分」等と選択肢にないものも答えるようになりました。
大事なのは、低いハードルだったとしても越えられたことに満足して褒めることです。
このころ、療育センターのグループワークや親の会、児童発達支援事業も利用しながら、私自身にもちょっとずつ知識が付き始め、子育てを楽しむ余裕が生まれてきていました。
次回、親子ともに楽になる「視点」の話はこちら。
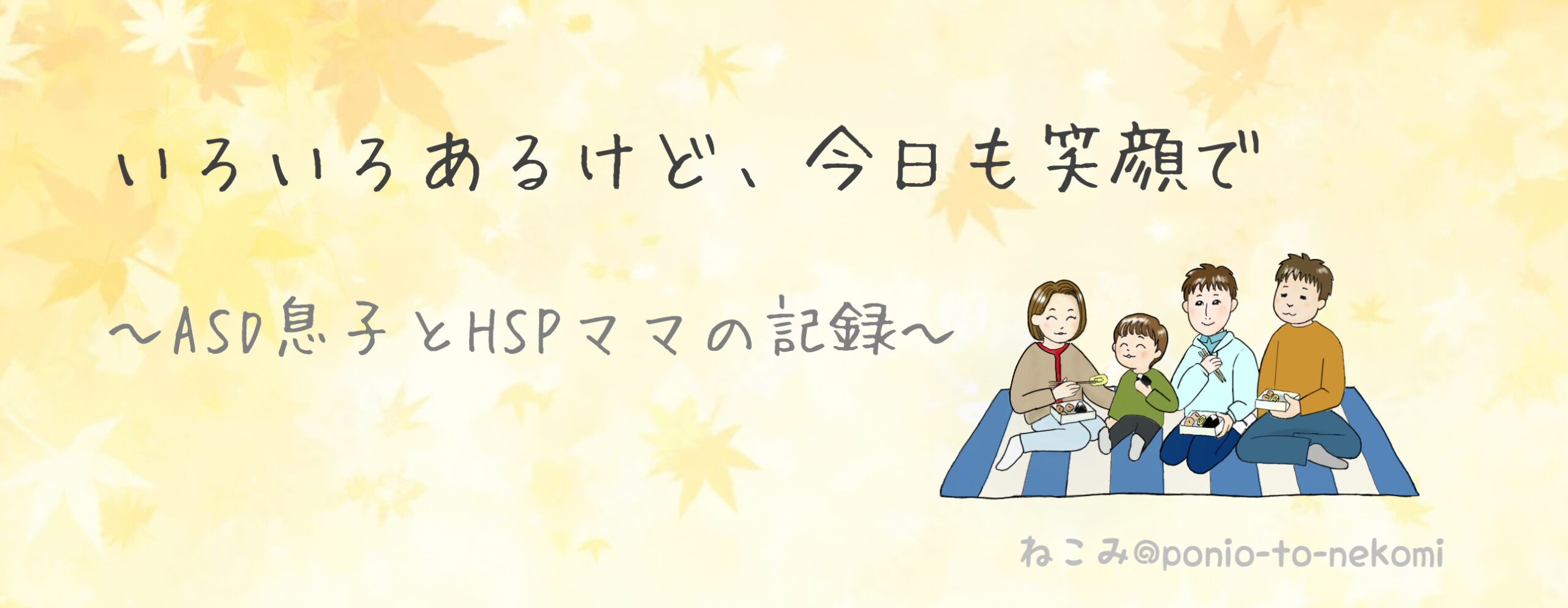
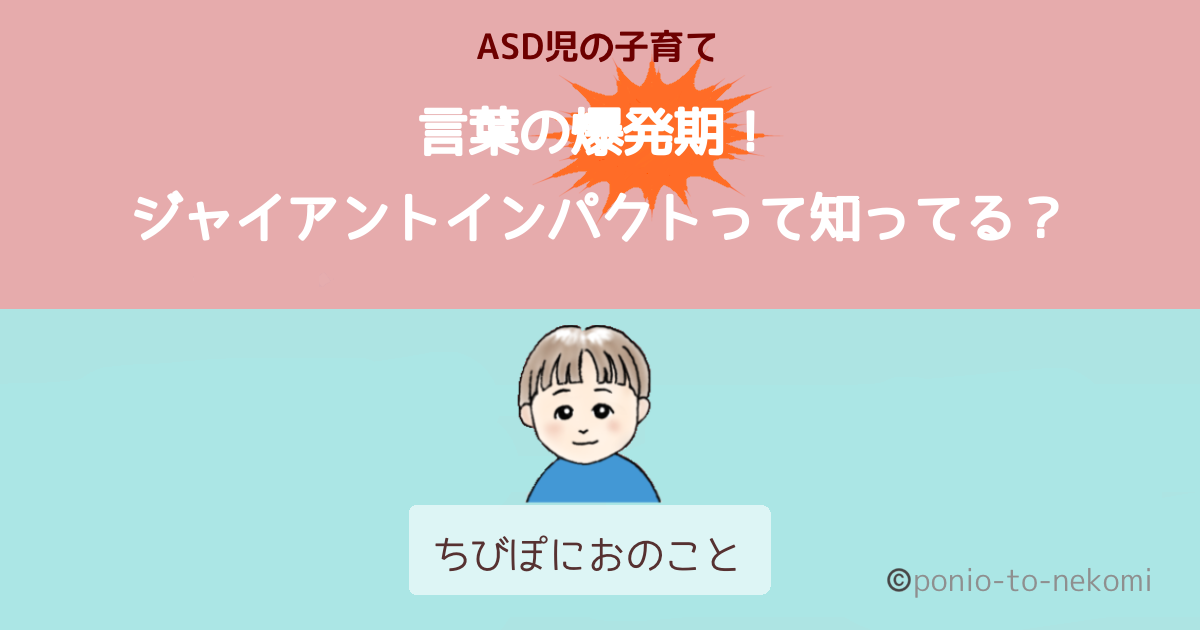


コメント