ねこみです。

これは、ぼくが主人公のお話だよ。
はむたは今までに片手では足りないほど、熱性けいれんを起こしています。
突発性発疹でも、アデノウィルスでも、手足口病でも、溶連菌感染症でも、インフルエンザでもけいれんしました。
母歴でいえば、そこそこベテランな私。でもこれだけ経験しても全然慣れない!毎回本気で怖かった。
この記事はそんなはむたの「何度経験しても慣れない熱性けいれん」との記録です。
同じように不安な思いをしている方に、少しでも心の準備になるように書きました。
初めてのけいれん(1歳)
令和元年生まれのはむた。保育園は0歳で入園しましたが、ちょうどコロナ禍に突入。世間はロックダウンやソーシャルディスタンスの真っただ中でした。保育士さんは皆マスクをしていて、家庭内もずいぶんと慎重に感染対策をしていました。
そのため、長男ぽにおに比べると、赤ちゃんの時に熱を出すことが極端に少なかったです。
1歳の春のこと。今までになく高熱を出したはむた。私は急ぎ、その日の午前にかかりつけの小児科に行きましたが、原因ははっきりとはせず(後日発疹が出たため、突発性発疹とわかりました)。
そして夕方。はむたは元気がなく、心配だったのでおんぶをして夕食作りをしているときのことでした。
背中のはむたが急に「ぎゃー」と泣いたあと、ぐったりと力が抜け、その瞬間、背中に「ピクピク」という振動が伝わってきました。
ただ事じゃない。
すぐにソファに下すと、はむたの眼球が上を向いたまま固定し、顔は真っ青。
けいれんを起こしていました。
母パニック!頼れる長男と再受診
まだ病院はギリギリ開いている時間。再びかかりつけ医に車で行くことに決めました。
意識が戻らず、ぐったりしたはむた。とてもチャイルドシートに座らせることなんかできません。パニックになった私を長男ぽにおが支えてくれました。
ぽにおは当時小学校5年生。まだまだ小さなその体で、次男をしっかり抱っこして一緒に車に乗り込みました。本当に頼もしかった…。
のちに、ぽにおはこの時を振り返って言いました。

すごく怖かったし、すごく心配した
ASDのあるぽにおは、それまで人に強い愛着を見せることはほとんどありませんでした。
けれど、はむたの誕生が、彼の中に「人を”心配する”とか”守りたい”という気持ちを芽生えさせてくれたと感じます。
そうして、駆け込んだかかりつけ。
でも、医師からは「よくあることです。熱が高ければ解熱剤を使って様子見て。」と言われました。
私は思わず聞きました。
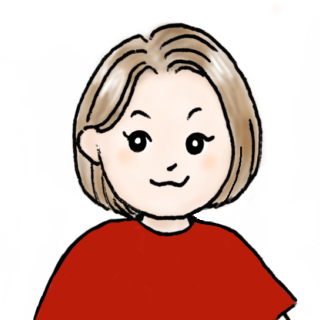
ダイアップはもらえないんですか?
実は昔、ぽにおも一度だけけいれんしたことがあるんです。その時は休日診療に連れて行って、ダイアップという、痙攣止めの座薬を処方してもらったので、今回も当然そうなるだろうと思っていたのです。
しかし医師からの答えは。
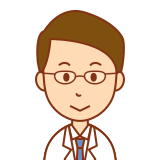
副作用があるから、あまり使わない方がいいんですよ
焦りと不安の渦の中、私はうなずくしかありませんでした。
胸をなでおろしたいのに、モヤモヤが残りました。
そして、夜…
再びのけいれん発作
時刻は23時ごろ、再びのけいれん。今度は1回目よりもずっと激しく、30秒ほど呼吸が止まってしまいました。
一日に2度のけいれん。これは、「脳の病気の可能性もありえる」という知識があったため、私の頭は真っ白に。
しかし、ちょうど居合わせた夫かぴすけが、けいれんを見るのがはじめてだったこともあり、私以上にパニックになっていて、それを見た瞬間、なぜか私は冷静になることができました。

はむた!おい、起きろー(泣)
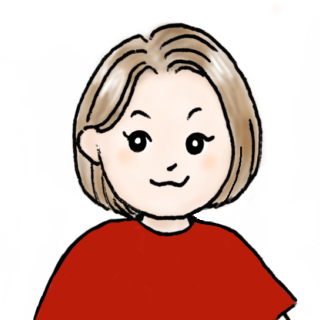
いや、楽に寝かせてあげて。けいれんが何分で終わるのか観察して。
母らしく、けいれんの時の対応を指示してから、119に電話。救急搬送が決まりました。
でも、夫がパニックになるのは無理もないのです。それは、はむたのけいれんが少々「派手」だからです。
眼球は上や横で固定し、呼吸停止に顔面蒼白。けいれんのあと意識がない時間も長い。
今まで何回も見てきましたが、「このまま死んでしまうんじゃないか」と、いつも本当に心配で、生きた心地がしないんです。
はじめての救急搬送とその後
はむたは、地域で一番大きな総合病院に搬送されました。
救急車の中で意識が戻ると、酸素濃度や血圧を測る機械を付けられるのが嫌で、大泣きしていました。
その声を聞いて、「泣く元気があったんだ」と胸をなでおろしたことを覚えています。
39度以上の熱があったため、まずはダイアップ(座薬)を使用し、30分後解熱剤の座薬を入れました。
ダイアップは2本処方され、1本は病院で。もう1本は8時間後使用しました。これでおおよそ24時間、けいれんを予防できるとのこと。
あとは、インフルエンザやコロナの検査ぐらいはしてもらったかと思うのですが、2時間ほど病院にいて、処置はそれくらいのものでした。
また、一日に2回のけいれんを起こしたので、脳の異常がないか調べるために後日脳波の検査をすることに決まったのでした。
(後編に続きます)
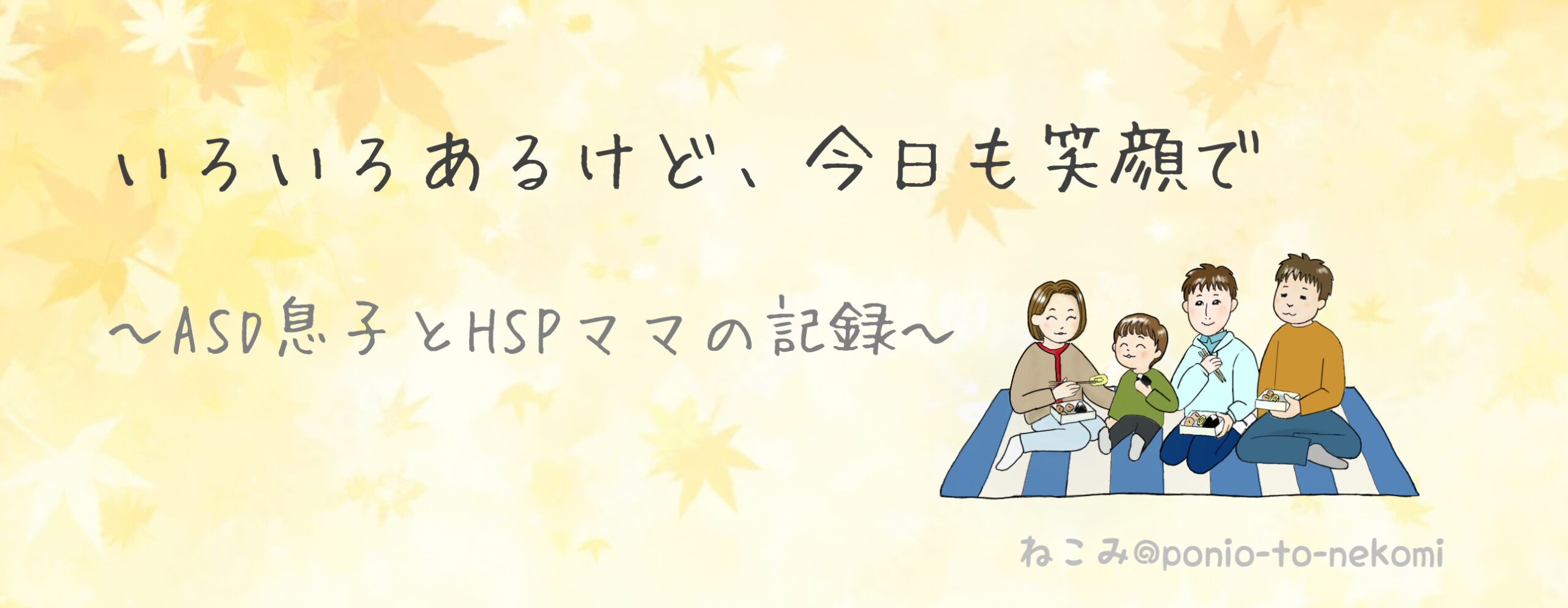



コメント